「白色ナンバーでも利用者さんの外出をお手伝い出来たらいいな。」
「ちょっとした送り迎えでも、白タク行為に捉えられちゃうからなぁ。」
と、思ったことのある介護関連の事業者さんはいないでしょうか?
日本は人や荷物を運送するためには、緑色や黒色などの営業用ナンバープレートと、有償でお客さんを運送するための二種免許が必要になってきます。
そのため、白色ナンバー(つまり自家用車)で、タクシー行為(お金をもらって人・物を運送する)は、違法です。
通称「白タク」と呼ばれます。
つまり、自家用車で利用者さんを運送するという行為は「白タク」に該当するため原則できません。
しかし、公共の福祉を確保するために、幾つか例外も認めらています。
そのうちのひとつが「ぶら下がり許可」になります。
この許可が下りると、一定条件下では白色ナンバーで普通免許しかなくても、利用者さんを運べるようになります。
これって介護施設を運営する事業者にとって、大きなメリットがありますよね。
そこで今回は「ぶら下がり許可」についての概要とメリットについて解説していきたいと思います。
この記事は…
- 介護施設を運営している事業者の方
- 現場を支える訪問介護士の方
- 訪問介護や介護タクシーの事業を拡大したい方
…などに読んでいただけると幸いです。
いわゆる「ぶら下がり許可」とは通称で、正式には「自家用車有償旅客運送」と言います。
この許可を受けると、ヘルパーさんが自家用車で利用者さんを送迎できるようになります。
ただし、許可を受けるには事業者は要件を整える必要があります。
さらには用途制限があり、利用者の要望をすべて応えられるわけではありません。
それでも、メリットが大きい「ぶら下がり許可」は、事業拡大にはもってこいというわけです。

では許可を受けるためには、どのような要件を満たせばよいのでしょうか?
許可要件は下記の通りになります。
- 介護タクシーの営業許可
- 訪問介護事業所の指定
「ぶら下がり許可」というからには、何かしらの本体にぶら下がって付随された許可になりますね。
そのぶら下がられた本体が「介護タクシーの営業許可」になります。
つまり、旅客の運送事業として認められた許可が必要になるわけです。
そのため本体とするのは「特定旅客自動車運送事業許可」でもOKです。
しかし、介護タクシーの営業許可の方が取得難易度が低く、金額も掛かりません。
また、介護タクシーの営業許可を得るには、旅客を運送するための「緑ナンバー車両」と「2種免許」が必要です。
そのため、「ぶらさがり許可だから、白色ナンバー&1種免許でいいんでしょ?」というわけではありません。
つまり事業所には、緑ナンバー車両と2種免許保持者が揃っている必要があります。

またヘルパーさんが在籍する事業所は、訪問介護事業所の指定を受けていなければなりません。
なぜならこの許可は、ヘルパーさんが日々の介護の際に、やむなく自身の自家用車に利用者を乗せていることを想定しているからです。
そのため介護業界では、ぶら下がり許可で運送している車両やその行為を「ヘルパータクシー」と呼ぶことも多いです。
さらには、訪問介護事業所として指定を受けるには、法人でなければいけません。
個人事業主として事業を行っている方は、ぶらさがり許可を取得することは出来ないので注意しましょう。
この「ぶら下がり許可」が下りたからと言って、誰でもどこへでも自由に運べるわけではありません。
運送するには下記のような条件があります。
- ケアプラン内の輸送にのみ適用
- 5台以上の使用には、運行管理者(国家資格)が必要
- 定員11名未満の乗用車であること
- 通院等乗降介助の申請が必要
まず大前提として「ヘルパータクシー」で利用者さんを運送するには、「ケアプラン」に基づく必要があります。
そのため利用するには介護認定を受けている必要がありますし、大多数の用途は「通院」になるでしょう。
ケアプランに記載された用途以外…例えば旅行や冠婚葬祭などのイベントには利用できません。
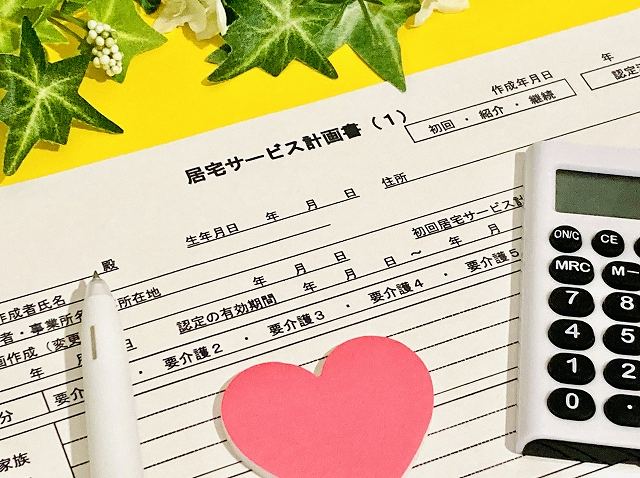
5台以上を使用すると、国家資格である運行管理者の配置義務が生まれます。
運行管理者とは、業務用自動車の安全運行のために、車両の管理やドライバーの指導監督を行う人のこと。
これはもちろん、一定以上の業務用自動車を使用するトラックやタクシー業界でも同じです。
この運行管理者は外部委託は出来ず、自社の人間が資格を保有している必要があります。
そのため、運行管理者の有資格者がいないのであれば、緑・白色ナンバー合わせて4台までにおさめましょう。
定員11名以上の自家用車で、もっとも現実的なのはマイクロバスです。
しかし、そのマイクロバスも初期費用や年間コストを考慮すると、よっぽどのバス好きでない限り、自家用にするのは割が合いません。
ぶら下がり許可は、あくまでヘルパーさんの「自家用車」を「やむない場合に」使用する想定です。
その「やむない場合」に使用する「自家用車」がたまたまマイクロバスだった、というのは大いに不自然。
事業所が事業用に用意した車両と捉えられても仕方ありません。
つまり「定員11名未満の自家用車」は、制度の悪用を防ぐためと言えるでしょう。
また、ぶらさがり許可は「ケアプラン」に基づいた運送のみが許可されています。
つまり、車の乗降りに介助が必要なる方が利用しており、「通院等乗降介助」の介護サービスの提供が前提です。
そのため、地域によっては乗降介助の協議申請が必要になる場合があります。
営業地域の監督役所に確認してみましょう。
では、ぶらさがり許可を取ることによって生じるメリットを確認してみましょう。
- 白色ナンバーの自家用車で利用者を運送できる
- 2種免許なしで、利用者を送迎できる
- ケアプラン内の送迎でもヘルパーが同乗できる
ここまでの記事で何度か「白色ナンバー&2種免許不要」はぶらさがり許可のメリットとして出てきました。
使用車両に全てに営業ナンバーの取得必要がないのは、事業所には大きなメリットです。
しかし、現場で最も大きなメリットは「ヘルパーが同乗できる!」という点でしょう。
どういうことかというと…
通常ケアプランに盛り込まれた送迎は「同乗禁止」です。
なぜなら、1人で通院できず、送迎してくれる介助者もがいないから、介護タクシーの送迎に介護保険の費用を使うことが出来るのです。
介助者が同乗すると、その前提が崩れてしまうことになります。
そのため、現場のヘルパーさんは「利用者を介護タクシーに乗せたあと、介護タクシーを自家用車で追いかけて、病院でまた乗降介助を行う。」という、面倒極まることをしなければなりません。
ところがヘルパータクシーでは、ヘルパーさん自身が運転&介助をこなせるため、面倒が一気になくなります。
つまり「ぶら下がり許可」は現場に則した緩和措置であると認識しましょう。

前述の通り、「ぶら下がり許可」は訪問介護事業とってメリットになります。
特にケアプラン適用の利用者が多いと感じている訪問事業所の場合は、真剣に検討してみましょう。
現場のヘルパーさんから、要望が上がっていませんか?
人手不足にならないためにも、早めの検討が必要です。
また、「ぶら下がり許可」を得るためには、介護タクシーの営業許可が必要となります。
これを機に、介護タクシーをサイドビジネスとしてスタートするのもひとつの選択と言えるでしょう。
いかがでしたか?
「ぶら下がり許可」は、現場に大きなメリットのある緩和措置です。
ただし、その恩恵をうけるためには「訪問介護事業所の指定」「介護タクシーの営業許可」が必要となります。
さらには運送目的もケアプランに基づくものと限定的です。
しかし、現場にはそれ以上のメリットがあり、事業者としても事業拡大の足掛かりにできる制度といえます。
訪問介護事業所や介護タクシーの事業をしている方。
是非、検討してみることをお勧めいたします。
この記事があなたの一助となれば幸いです。

またビスタサポートでは、介護タクシーの開業支援事業を行っています。
- 介護タクシーを開業したい方
- 介護・医療スキルを活かして起業を目指したい方
- 既に介護・看護の事業を行っているが、サイドビジネスも考えている方
- 第二の人生のため、何かしらのビジネスを検討している方
…などなど、介護タクシーに狙いを定めている方でも、はっきりとしたビジョンが無い方でもOKです。
まずは、下記のページから弊社ビスタサポートに無料資料請求してみましょう。
あなたのお悩み、ビスタがしっかりサポートさせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。






二種免許はないけど
介護タクシーに興味有ります
宜しくお願いします
コメントありがとうございます。
介護タクシーは自分のペースでお仕事ができるので、とてもおすすめな仕事ですよ^^
もしよろしければ開業方法の資料も無料で配布しておりますので、そちらをご覧ください。