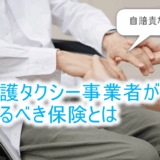「介護タクシー事業も軌道に乗ってしばらく経つし、増車したいな。」
「忙しくて手が回らなくなってきた。これ以上は人を雇って車を増やすしかない。」
そう考えている介護タクシー経営者の方もいるでしょう。
収益アップのために「もう増車するしかない」という状態になっているのは、事業が成功している証でもあるので喜ばしい事です。
しかし、介護タクシーは開業時に許可を得たように、増車時にも変更届などを申請しなければなりません。
では、何の書類が必要で、どのような流れで手続きすることになるのでしょうか?
そこで今回は、介護タクシーの増車時に必要な手続きについて解説したいと思います。
この記事は…
- 介護タクシー事業を拡大したい方
- 収益アップを狙っている介護タクシー経営者
- 介護タクシーでの起業を志している方
…などにお読みいただけると幸いです。
介護タクシーの増車は単に「車両を増やせばいい」というわけではありません。
車両を増やそうにも、それを収める車庫が必要ですし、送迎する運転者も必要になります。
つまり、車両、車庫、運転者の3つが新たに揃う目途がつくようなら、増車を具体的に計画しましょう。
そして何より事業拡大の「認可」を受ける必要があります。
改めて認可を受けるためには、3つそれぞれが要件を満たしている必要があります。
簡単に確認していきましょう。

介護タクシーの車両については、難しい条件はありません。
営業車の条件は「普通乗用車」であることのみです。
つまり貨物車や11人乗り以上の乗用車は使用できません。
なお、介護タクシーでは軽自動車の使用も認められています。
また介護タクシーを営むにあたり、車イスやストレッチャー対応の「福祉車両」を用いることを強くお勧めします。
利用者と運転者双方の身体的負担が軽減され、移乗にかかる時間も削減できます。
増車にあたり、車庫の要件は厳しく審査されます。
- 自己所有の土地、もしくは1年以上の賃貸
- 車がはみ出ない広さ
- 狭すぎない前面道路
- 清掃・整備が出来る設備(水道が必要)
他にも営業所からの距離や土地の用途、各種法令に違反していないか…などが審査されます。
介護タクシーに限らず、お客さんからお金を貰って運送するには「2種免許」が必要です。
新たに雇うならば、2種免許の有資格者にするか、取得させるかのいずれかになります。
また、介護職員初任者研修をはじめとする介護系資格は、努力義務なので、絶対に必要というわけではありません。
ただし福祉車両を用いない場合は、介護系資格も必須となりますので注意してください。

そもそも介護タクシーの増車とは、事業の拡大のために行うもの。
つまり、許可を受けた時の事業計画を変更する行為です。
そのため増車時には「事業計画変更届」を提出、もしくは「事業計画変更認可申請書」を申請する必要があります。
では、この「届出」と「認可」で何が違うのか見ていきましょう。
既に、増車分の車庫が運輸局に許可されている場合が「届出」に該当します。
つまり開業時に、増車を見越して複数台のスペースを車庫として申請し、許可されたパターンです。
このパターンは自己所有の土地に多いです。
このような場合では、すでに許可を得ているため「届出」だけで済みます。
届出書に押印を貰えれば、その日のうちから新しい車両も営業することが可能です。
多くの方は「認可」を申請することになるでしょう。
なぜなら、介護タクシーは1人1台で起業することがほとんど。
自己所有の土地であっても、事業の見通しが立たないうちから、複数台分の車庫を申請しておこうという方は稀なのです。
賃貸の場合は増車まで賃料分が無駄になるため、なおさらですね。
ちなみに「認可」を受けるのは「車庫」であり、車ではありません。
つまり増車時の最大焦点は「車庫」。
車両は後で届出するだけでOKです。

ここからは「認可」パターンの説明を行います。
実際に増車をする時の手続きの流れは、下記のようになります。
- 新しい車庫と車両の準備
- 関係書類を揃えて、「事業計画変更認可申請書」を申請
- 運輸局での審査(1~2か月待ち)
- 車庫の「認可」後に車を購入orリース
- 車両を用意したら、増車を届出する
まずは新たな車庫の準備を進めてください。
あくまで「車庫を拡大する」という「事業計画」を申請するものだからです。
増車はその結果に過ぎません。
そのため、車両や付属するタクシーメーター、任意保険は見積りだけでOK。
また、車庫に関しても賃貸であれば、「認可が下りたら」の条件付きで契約すると良いでしょう。

- 一般乗用旅客運送事業の事業計画変更認可申請書
- 事業計画新旧対照表
- 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
- 増設した車庫の各種図面と写真
- 車庫の不動産登記簿謄本か賃貸借契約書
- 車庫前の前面道路の幅員証明書
- 各種見積もり(新しい車両、任意保険など)
- 各種宣誓書
申請に必要な主な書類は以上になります。
以上の様式のほとんどは、管轄運輸局のホームページからExcel方式でダウンロードできます。
記載例もシート分けされて用意されていますので、しっかりと確認して記載しましょう。
- 幅員証明書は廃止されている自治体もある
- 車両の購入は認可後
- 資金計画はしっかりと
申請に必要な「幅員証明書」ですが、自治体によっては廃止されている場合があります。
このような自治体の場合は、代わりになる「前面道路の宣誓書」を記入して提出することになります。
道路の幅や歩道の有無等を記載する欄があるため、必ず調査を行う必要が出てきます。
また証拠として、調査時の写真を添付するよう求められることがほとんどです。
事実と異なる宣誓をした場合、最悪許可が取り消しなっても文句は言えません。
増車の為の新たな車両は、車庫の認可が下りてから購入(もしくはリース)しましょう。
購入したけど認可が下りなかった…となったら目も当てられません。
中古で購入予定の方は、認可までの期間を取り置きしてもらえるよう、手付金などを支払っておくと良いでしょう。
福祉車両の中古車は業界で人気のため、品薄状態が慢性化しています。

事業計画変更を申請する際には、資金要件が無いので銀行口座の残高証明は行われません。
だからといって、ざるな計画を立ててはいけません。
実際には、少なくない金額がかかりますからね。
車庫の賃貸、車の購入、増車後の維持費などなど…
無理のない計画で収益アップに繋げていきましょう。
いかがでしたか?
介護タクシーの増車は、手続き的には新しい車庫の認可を得るのがメインの作業になります。
要件を満たすよう準備を行い、審査に備えましょう。
それと並行して、マーケティング戦略を練る必要があります。
なぜなら、1台体制から2台体制になると、出来ることが格段に増えるからです。
事業の拡大戦略を改めて考えていきましょう。
この記事があなたの一助となれば幸いです。

またビスタサポートでは、介護タクシーの開業支援事業を行っています。
- 介護タクシーを開業したい方
- 介護・医療スキルを活かして起業を目指したい方
- 既に介護・看護の事業を行っているが、サイドビジネスも考えている方
- 第二の人生のため、何かしらのビジネスを検討している方
…などなど、介護タクシーに狙いを定めている方でも、はっきりとしたビジョンが無い方でもOKです。
まずは、下記のページから弊社ビスタサポートに無料資料請求してみましょう。
あなたのお悩み、ビスタがしっかりサポートさせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。