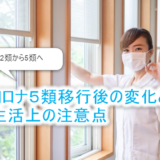様々な客層がいる中から、ターゲティングで自社の商品やサービスの強みが活かせる顧客を選ぶ。
言うのは簡単ですが、やるのは難しいですよね。
というか、実際に何から始めればよいのか迷うと思います。
さらには、マーケティングに馴染みのない方には聞きなれない単語も多いでしょう。
ともすれば、敬遠してしまいがちになるマーケティングですが、独立や起業を目指す方には避けて通れない道であることも確かです。
なぜならマーケティングの可否が起業の成功・失敗につながるといっても過言ではないからです。
そこで今回は、前回の「STP分析」の「セグメンテーション編」に引き続き「ターゲティング編」をお届けしたいと思います。
この記事は…
- 起業を志している方
- マーケティングに興味のある方
- 思うように顧客が増えずに困っている経営者の方
…などにお読みいただけると幸いです。
狙いを絞って効率よく売上を伸ばしましょう。
まずは、前回のおさらいを兼ねて、STP分析について簡単に説明します。
STP分析とは、マーケティングの手法の一つ。
- segmentation(セグメンテーション)…市場の細分化
- targeting(ターゲティング)…標的市場の決定
- positioning(ポジショニング)…他社との棲み分け
まずは市場を分析して細分化し(segmentation)、参入する標的市場を決めて(targeting)、市場内で自社の位置取りを確立(positioning)する、といった流れで進めていきます。
この参入する標的市場を決めることこそ、ターゲットマーケティングの第一歩。
標的市場とは、狙いうつ顧客層のことを指します。

この顧客層は、前段階の「セグメンテーション」で区分けされています。
区分けする方法は、年齢や性別、趣味・嗜好、地理的・気候的条件など様々です。
「ターゲティング」では、この様々な要因で区分けされた顧客層から、購買意欲が高いであろう顧客層を絞り込むのが目的となります。
市場全体に働きかけるマスマーケティングと異なり、ターゲットマーケティングは購買意欲の高い顧客層に絞ってアプローチするため効率が良いのです。
- 自社商品やサービスを効果的にアピールできる
- マーケティング戦略の策定・実行がしやすい
- 広告宣伝費が削減できる
商品を買う前の顧客やサービス提供を受ける前の顧客は、「悩みを抱いているが解決方法を知らない、もしくは探している状態」です。
つまり、その顧客には求めるもの…「ニーズ」がある状態です。
その状態の顧客をターゲティングで、適切に絞り込むことで自社製品やサービスを効果的にアピールできます。
また、顧客視点からは自分の悩みを解決したり、欲求を満たすような広告が自然に目に入るようになります。
顧客の中には、販売員から直接セールスをされると引いてしまうような方も多くいます。
そのような方には「自然に目に入る」事の方が購入のきっかけになるのです。
さらには、狙いが絞られているためマーケティング戦略を決めやすく、実行もしやすいというメリットがあります。
つまり顧客層に合わせてPRの仕方を柔軟に変化させられます…若年層に新聞広告は非効率的ですよね?
また、市場全体に働きかける必要がないため、広告経費を削減できるのもメリットです。
資金の豊富にある大企業ならまだしも、限りある資本の無駄打ちは避けるべきです。
起業したてならばなおさらでしょう。

また、マーケティングを勉強している方には「ペルソナ」という用語にも聞き覚えがあると思います。
この「ペルソナ」と「ターゲティング」は着眼点が似ているところがあります。
ペルソナを活かしたマーケティングも存在するため、違いを説明しておきましょう。
まず「ペルソナ」とは、実際に存在する顧客データーの分析を基にして作られた「商品やサービスを利用する対象モデル」です。
要は、企業が設定した利用者モデルです。
ただし前述の通り、実際の顧客データーが基になっているため信頼性が高いのが特徴です。
以上を踏まえてた「ターゲット」と「ペルソナ」の違いは以下の通り。
- ターゲット…顧客層として標的にすべき実在する集団
- ペルソナ …ターゲットの解像度を高めて具体化した人物像
マクロ視点で市場や集団全体を見るのがターゲティングであるのに対し、ミクロ視点で個々の顧客を見るのがペルソナであると言えます。
そして「ペルソナマーケティング」は、企業が特定のペルソナに基づいて商品やサービスを開発・提供していく手法になります。
より具体的な人物像を描くことで、ニーズや問題点を細かく洗い出し、より効果的なマーケティング戦略を展開しようという狙いがあります。
ただし、顧客像を絞りすぎると、市場全体のニーズを見逃すリスクが潜んでいるので注意が必要です。
実際にターゲティングする際には、「6R」と呼ばれる6つのフレームワークを用いるのが有効とされています。
- Rank/Ripple Effect(優先順位/波及効果)
- Realistic scale(市場規模の有用性)
- Reach(到達可能性)
- Response(反応の測定可能性)
- Rate of Growth(市場の成長性)
- Rival(競合状態)
これらは「セグメンテーション」で出てきた「4R」とも被ります。
ちなみに、ターゲティングで加わるのは5番の「市場の成長性」と6番の「競合状態」になります。

セグメンテーションされた市場に優先順位を着けていきます。
まずは自社が重視する項目について、それぞれ順位付けすると良いでしょう。
また、顧客からの事業への関心度(優先度)の高い市場を選択すると、SNSなどの波及効果で一気に多くの顧客へアプローチすることができます。
自社の製品やサービスを爆発的に普及する可能性があります。
市場規模の有用性とは、選ぶ市場規模が適しているのかどうかになります。
例えば、市場規模が小さければ、事業継続に必要な売上が確保できません。
反対に大きすぎると、競合他社も多く、マーケティングに時間と費用がかかり、効率的とはいえません。
つまり、自社に合った適切な市場規模が望ましいのです。
企業のマーケティング施策が、どれだけ効果的に市場へアクセスできているかを評価します。
また、商品やサービスが狙った顧客へ物理的に届くかどうかも含みます。
どんなに良いターゲットを見つけても、商品が届かず、売り上げに繋がらないのでは意味がありません。
「マーケティングの効果が測定できるかどうか」という意味です。
つまり、効果が測定できないと、施策の評価も出来ません。
現在行っているマーケティングがあっていたかどうかもわかりません。
効率的なアピールをするためのマーケティングですから、効果を測定する必要があるのです。
長期的に安定した利益を得るためには、成長性のある市場を選ぶ必要があります。
例えば、出来たばかりの市場で現在の顧客層は少なくても、1年後に将来10倍の顧客が生まれると期待出来れば、参入もありでしょう。
そればかりか、先駆けすることによって、大きな利益を確保できるかもしれません。
反対に、現在は良くてもすぐに先細りが見えている市場に参入するのは、見送った方が無難です。
コロナ禍のマスク事業などがそれに当たります。

その市場にどのくらいの競合他社が存在するか?その他社はどの程度のシェアを誇っているのか?などを見ていきます。
当たり前ですが、なるべく競合は少ない方が良いでしょう。
必ず競合他社の売上やマーケティング戦略は調査・分析するべきです。
そして、自社が差別化できるポイントを見つける必要があります。
STP分析の「ポジショニング」にも関わってくるでしょう。
6Rのそれぞれの要素はそれぞれが独立しているわけではありません。
相互関与しているため、ターゲティングする際はバランスよく考えることが大事です。
例えば「市場規模は大きく、到達性も良い。だからこそ競合他社も多い。」という市場や「市場規模は適正で競合もいない。ただし、海外のため到達性は悪い。」といった市場もあるでしょう。
このように、それぞれの要素全てを満たす市場を見つけるのは困難だと、肝に命じておきましょう。
そのなかで、総合的に見てよりよい市場を選択していく事が大切なのです。
ターゲティングは自社に有利な市場を探し、勝負する土俵をきめるために行います。
それと同時に大切なのが、そのターゲットをどう攻めるのかのマーケティング戦略になります。
主なマーケティング戦略は3つ。
- 集中型マーケティング
- 無差別型マーケティング
- 差別化マーケティング
集中型マーケティングは、ターゲティングした一つの市場に対して、集中的にマーケティングを行います。
自社の強みを活かせる市場セグメントに焦点を当てているため、経営資源に限りのある小規模企業に有効な戦略です。
セグメント内に自社のブランドイメージを植え付け、市場でのシェア拡大を目指しましょう。
とくに、特定商品やサービスを持つ企業、特化したニーズに対応できる企業などの戦略にピッタリです。
ただし、この戦略は特定の市場セグメントに、自社資源を集中投資していることになります。
そのため、そのセグメントの盛衰に左右されるリスクを忘れてはいけません。

無差別型マーケティングは、特定の市場セグメントを対象とせず、幅広い顧客にアプローチする戦略です。
つまり、広範囲の顧客に一般的な製品やサービスを提供する、従来型の戦略とも言えます。
テレビやラジオ、新聞などの伝統的なマスメディアを通じて広告が行われます。
いわゆる「マスマーケティング」ですね。
主に大企業が広範囲な市場に製品を展開する時に用いられます。
というか、伝統的メディアでの広告や多くの市場に商品を流通させるには莫大な資金が必要なため、実質的に大企業以外では困難な戦略でしょう。
多くの人に受け入れられやすい日用品や食品などの広告に適しています。
しかし、ニーズが細分化されている昨今では、通用しづらい戦略とも言えます。
差別化マーケティングは、ターゲティングした複数の市場セグメントに、それぞれ合わせたマーケティング戦略を展開する手法です。
セグメントが異なれば、当然ニーズも異なります。
そのため、それに合わせたマーケティングをして、ニーズに合った製品やサービスを用意する必要があります。
例えば、内容が同じサービスでも提供時間により料金を変えたり、類似商品の機能を変えたりして販売しています。
差別化マーケティングは、複数のセグメントにニーズに対応したアプローチできるのが最大のメリットです。
しかし、この差別化マーケティング体力のある企業だからこそ出来ることだと心得ましょう。
経営資源に限りのある小規模企業にはあまり向かない戦略です。
ビスタサポートでは「介護タクシーの学校」をWebサロンで開設しています。
このサロンは、介護タクシーの運営ノウハウのほか、起業やマーケティングに対する心得も網羅しています。
これから起業を志す方へピッタリの内容となっております。
また、Webでの受講のためご自宅で好きな時間にご視聴いただけます。

30代…若くして社長になりたいアナタ。
40代…今の会社に勤めたままでは将来の不安がよぎるアナタ。
50代…定年が迫ってきて、第二の人生の生き方を模索しているアナタ。
60代…今まさに第二の人生を豊かにしたいアナタ。
自分の人生の何かを変えたいアナタは、是非一度、ビスタサポートの介護タクシーの学校をご覧ください。
内容も毎月更新。サブスク形式でお届けしています。
起業を志している方や起業して間もない方は、経営資源にあまり余裕はないと思います。
まずはターゲティングで適切な市場セグメントを選択して、経営資源を集中投下するのが定石です。
そして、そのセグメントでポジションを確立したら、段階的に繋がりのあるセグメントに販路を拡大していくのがターゲティングの基本戦略だと言えるでしょう。
いかがでしたか?
今回はターゲティングの仕方や戦略について紹介しました。
この記事があなたの一助となれば幸いです。
また、ビスタサポートは地域の介護・医療のサポート企業として、日々活動しています。
移動でお困りの方。
日々の送迎に苦労されているご家族様。
ビスタサポートへお声がけください。
救急救命士による安心安全な送迎をお約束いたします。
そのお困り、ビスタが解決します。
最後までお読みいただきありがとうございました。